「もう、辛くていけません」
これは、中学進学を迎えたばかりのゴールデンウィークにIくんがつぶやいた言葉。
その言葉から1年。保護者・先生・専門家でどのように「自分らしく登校する」に繋げたか、その奇跡の事例をまとめました。
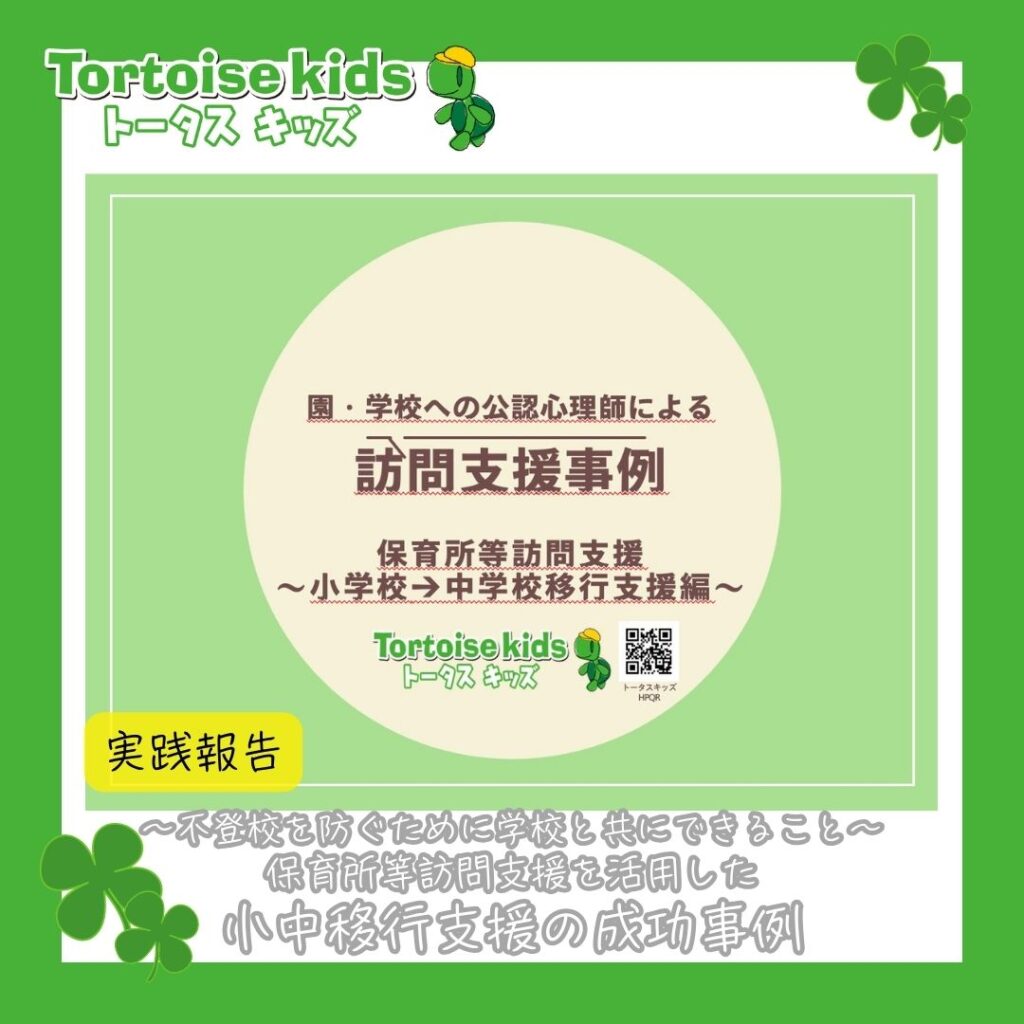
<中学校入学まで>
Iくんは小学2年からトータスキッズに通い、5年生から保育所等訪問支援を開始。集団行動が難しかったIくんも、6年生の頃には成長と先生方の工夫による支援環境づくりのおかげで、交流級でも楽しく活動できるようになっていました。
「もう、辛くていけません」
これは、中学進学を迎えたばかりのゴールデンウィークにIくんがつぶやいた言葉。
小学2年からトータスキッズに通い、5年生から保育所等訪問支援を開始。集団行動が難しかったIくんも、6年生の頃には成長と先生方の工夫による支援環境づくりのおかげで、交流級でも楽しく活動できるようになっていました。
けれども中学では、その成長ゆえに「困っていること」が伝わりにくくなり、先生方も支援の必要性を捉えづらくなっていたのかもしれません。
<専門家・先生・保護者の協働>
そこで再開された訪問支援。
これまでの歩みを振り返り、
どんな支援が有効だったのか、
小学校と中学校の違いを整理し、
新しい環境での改善策を出し合いました。
保護者、先生方、そして私たち専門家。
それぞれの想いと知恵を重ね合わせ、
「自分のペースで通える学校環境」を一緒に築いていきました。
その積み重ねが、Iくんの安心を支え、少しずつ前に進む力を育てていきました。
<Iくんの今>
1年経った今、Iくんは先生と一緒に1日の流れや1か月の予定を確認しながら、安定して学校に通えています。交流級にいる時間も少しずつ増え、笑顔も戻ってきました。
この事例に共通するのは、
「やってみよう」と動いてくださった先生方と、
「できることを支えます」と動いてくださった保護者の存在。
先生の工夫が子どもの変化を生み、
その変化が保護者の安心につながり、
安心が先生への信頼となって支援を後押しする。
理想的な好循環が回っていたのです。
<訪問支援の意義>
保育所等訪問支援の意義は
「個に合った支援環境構築を通して、集団生活を豊かにすること」。
子どもの成長を支えるだけでなく、
先生の「できた!」を増やし、
保護者の安心を広げる。
そして、そこにある集団も豊かにする。
もちろん、すべての子どもにとって学校が最適な場所とは限りません。
けれど、適切な支援環境があれば、
不登校を防ぐことができるケースは確かにあるのです。
<教育委員会・先生方へ>
義務教育は、子どもに与えられた大切な権利。
その権利を活かすために、専門家・教育委員会・学校が手を取り合い、
一人ひとりの「行ける」「やりたい」を支える環境を共に築いていきたい。
この取り組みは、一人の子を支えることを超え、
地域全体の学びを豊かにする力になります。
もし「この取り組み事例を詳しく知りたい」「一緒に不登校支援に取り組もう」と思ってくださる教育委員会や先生がいらしたら、ぜひお声がけください。
*園・学校で子どもの「できた!」を増やしてあげるには?そんな方には通所での個別指導(児童発達支援or放課後等デイサービス)と園・学校での行動観察等(保育所等訪問支援)との組み合わせがおすすめです。個別と集団両面で、できるを増やす支援環境をサポート。
利用ご希望の方、詳しくはトータスキッズまで。

**************
「困った…」を
「できた!」に変える支援の場
トータスキッズ
**************
#ASD #ADHD #発達障害 #発達凸凹 #知的障害 #自閉症 #自閉症スペクトラム
#療育 #ABA #個別指導 #応用行動分析 #ペアレントトレーニング
#児童発達支援 #放課後等デイサービス #安心できる場所 #横須賀 #子育て
#子ども #自己肯定感 #不登校支援 #小中移行支援 #学校とつながる #教育委員会連携 #先生と共に #学びを支える #地域で育つ #保育所等訪問支援 #支援の輪を広げる #wonderforest #成長の物語